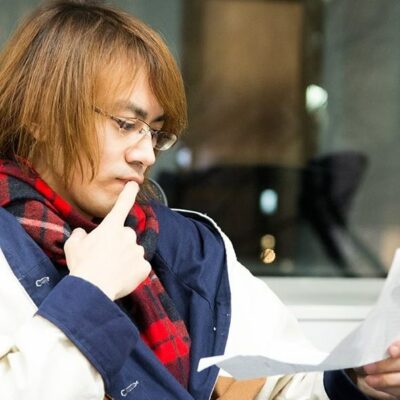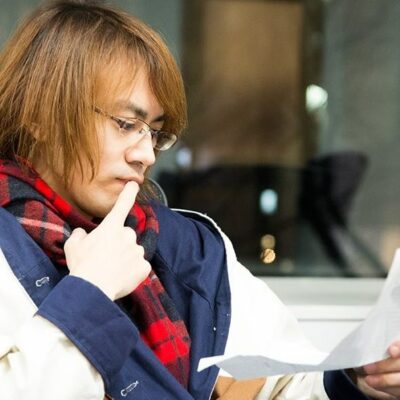落ちているボールを拾う、という比喩がある。職場で使われるときはもっぱら、ボールという言葉は仕事を意味している。
だから、落ちているボールを拾うという比喩は、誰も手をつけていない仕事に自ら手をつける、ということを指す。ボールというくらいだから、だいたいそれは軽微な仕事に限られる。
落ちているボールを拾うことは、基本的にはいいことだとされている。ボールが落ちていては、仕事が進まない。
ちょっと資料を直したり、誰かに依頼の連絡をしたり、スケジュールを引き直すほどではない、小さな仕事は日々たくさん生まれる。会議の終わりには「これは誰のボール?」と聞いて、TODOが零れ落ちないよう確認したりする。
それでも落ちてしまうのがボールというものの(つまり仕事というものの)困った特性で、拾ってくれた人には「拾ってくれてありがとう」と声をかけることもある。
落ちるボールはさまざまだが、誰でもできるようなものが多い。
会議がはじまって、「議事録は誰がとる?」といった瞬間にボールが一つ放られる。「ぼくやりますよ」といって拾われる。そういうふうにすぐに拾われるボールはまだいいほうで、新たに報告された小さな不具合、長年見過ごされていた誤字脱字、年に一度の棚卸作業などなど、「そろそろこれ手をつけないとね」という類の仕事は、会社が大きくなればなるほど、不思議なほどに増えていく。気づけば床にはボールが散乱している。
ボールは善意によって拾われる。仮にあらかじめ対処すべき人が決まっていたなら、それは「落ちたボール」ではなく、ただその人が仕事をやり忘れていただけ。だから、ボール拾いはかならず誰かの善意によってなされている。
しかし、そうした献身的な見栄えとは裏腹に、ボール拾いにはさまざまな問題がつきまとう。どういう問題が起きるのか、どう対処すればいいのか。
もともとボールを拾いがちだったという、リブセンスの社員Aさんと一緒に考えてみた。
ボール拾いは宣言されない仕事
「性格診断をすると、擁護者とかサポーターって出るんですよね。だいたい看護師のイラストで、いかにもケアしてそうな人。そういう人にボールって集まるな、と思います」
ボールを拾う習性は、Aさんの性格によるところもあったようだ。はじめにボールを拾う人の不利益について聞いてみた。きっとボールを拾うことは、いいことばかりじゃないはずだ。
「派手な仕事につながらないな、と思います。なにか不具合やミスがあったから、それを直さないと、っていう仕事はやっぱり評価されづらいですよね」
一つめの問題点は、評価との相性が悪いことだ。どのような人事制度を導入するにせよ、目標を掲げて成果主義で評価するものはみな、ボール拾いと相性が悪い。
Aさんのいう「派手な仕事」を目標への貢献度と言い換えてみるとよくわかる。計画にびしっと引かれた目玉の施策を成功させることは、会社を成功へと導くだろう。派手な仕事とは、必ずしも売上を生む仕事とは限らない。バックオフィスにもインフラエンジニアにも派手な仕事はあり得る。
ボールを拾う仕事は、そういうものではない。単体の成果や結果が期待された仕事ではなく、だいたいがその付随物や、副作用の後処理、不具合の補修のようなものだ。単体として成立するものでなく、何かの仕事を成立させるための、補助的な仕事であることが多い。
縁の下の力持ちとしてチームを支えているが、それ自体が独立して目標に寄与するわけではない。
「ボール拾いって、やるって宣言してやる仕事じゃないですよね。チームとしては目標を宣言して、それに向かって仕事に取り組んでいるんですが、そもそも宣言されない仕事は見えないし、やったところで評価されづらくて」
この「宣言されない仕事」という呼称は、ボール拾いの特徴を的確に表している。ボール拾いは「生産性の低い仕事」とか「目標への寄与が小さい仕事」ではない。一番の特徴は、それが周縁的かつ補助的で、無くてはならないにもかかわらず、公に評価されづらいということだ。
これはオーストリアの哲学者イヴァン・イリイチが〈シャドウ・ワーク〉と呼んだものによく似ている。
イリイチは家事や通勤の時間など、それ自体賃金が支払われないにも関わらず、賃労働を成立させるのに欠かせない条件となっている仕事をシャドウ・ワークと呼んだ。この語は、それまで労働と考えられていなかった家庭の活動等を労働(ワーク)の一種と捉え直したことに由来している。
ボール拾いには賃金が支払われているから、シャドウ・ワークとは言い難いが、両者はいくつかの類似点を共有している。ふつうの仕事(賃労働)とシャドウ・ワークを比較して、イリイチはこんなことを述べている。
賃労働に就くためには、仕事に自ら申し込み、合格して取り組むが、シャドウ・ワークの場合は、性分や生まれついての属性によって就くことが求められる。賃労働において人は選抜されるが、シャドウ・ワークの場合は、人はただその場に置かれている。 [1]
シャドウ・ワークもまた「宣言されない仕事」の一つだといえる。共通するのは、自らその仕事を選び取ったのではなく、やらざるを得ない仕事だということだ。
冒頭で、ボールは善意によって拾われていると書いたが、それをここでは一部訂正しなければならない。半分は確かに善意が働いているかもしれないが、もう半分ではボールはやむを得ずに拾われているのだと。
その証に、Aさんはこんなことも述べていた。
「落ちているボールを拾わずに放置するって難しいんですよね。チームが困りそうだったら、つい手を出してしまうんです」
こういうケースは多いだろう。誰かが困りそう、仕事がつまづきそう。そういう予見のもとに、積極的にボールを拾ってしまう。能動的になされているようで、受動的になされている一面もある。
そしてAさんはこう付け加えた。
「でもそれって仕事の優先順位とはかならずしも一致しないんです」
ボールを拾う人たちは親切な犠牲者なのか
評価のされづらさは、ボール拾いの困った特徴だが、きちんと評価を行えば問題は解決するかといえば、そうではないとAさんは語る。これが第二の問題点である。
「ほんとうは拾わなくてよかったボールもあるんですよね。仕事ってリソースが限られているから、できる中で優先順位をつけていくべきで、何をするか、何をしないかを考えなくちゃいけない」
それにも最近は慣れてきたというAさんだが、昔はそうではなかった。持ち前の気質に加えて、これまでの職場ではそれが当たり前だったことも影響していた。小さな仕事に注意を奪われて、チームの優先順位ではなく、自分の優先順位で仕事をしてしまうこともあった。
加えて、こんな背景もあったという。
「ボール拾いを自分の居場所にしちゃったこともありましたね。成長とか目標とかには寄与できなくても、困ってる人にはありがたがられるので。手頃な達成感になっちゃいますよね」
ボールを拾うとチームに感謝される。ほとんどの人はボールを拾いたくないが、それを誰かがやらなければいけないことはわかっている。だから誰かが拾ってくれることに感謝を表明する。「ありがとう」「助かるよ」という声が気休めになる。
しかし、同僚の感謝と仕事の成果は、かならずしも一致しない。
思うように成果があがらず、自分の価値を信じられないときこそ、受け取る感謝は甘美である。そこに逃げ込んでしまいやすい。
大きな成果をあげるための努力と研鑽に励むかわりに、落ちているボールを拾い続ければ、成果はますます遠のくばかりだ。やるべき仕事から目を背けて、せっせと人助けに励む。そういう道は、短期的には安心するかもしれない。
ただしその道は長くは続いていない。いつまでも続ければ、いずれは「拾わなくてもいいボール」まで拾ってしまうことになるし、成長や評価のギャップに苦しむことになる。
ボール拾いを逃げ場にすれば、どこかでかならず行き詰まる。
さらに第三の問題として、チームの側のリスクもあるとAさんは言う。
「これは自分じゃない人を見ていて思った話なんですけど、誰かがあまりにボールを拾いすぎると、まわりもボールを拾ってもらうのがあたりまえになって、その人が居なくなったときにチームが崩壊しちゃうんですよね。そういうケースをたくさん見てきました。お互いに依存しちゃうんです」
献身的なボール拾いは、当人だけでなくチームにも弊害をもたらす。
仕事は宣言され、分担が明示されることによってチームワークが成立する。落ちているボールを拾い続けることは、短期的にはチームメンバーに喜びを与えるかもしれないが、それは彼ら彼女らが負担すべき労役を暗黙的に引き取って不可視化する。
いつからかチームメンバーは、ボールを拾わない、意識しない、誰かに拾ってもらうことが当たり前になっていく。
不可視化された仕事は、自分たちのやらなくていい仕事なのだと、意識の裏側に滑り込む。チームはボールを拾う人に依存する。
依存するということは、依存される側が居場所を得ることを意味している。両者の思惑は一致する。
こうして黙々とボールを拾う人と、それを黙って見ている同僚は、この構図の共犯者となって、落ちたボールをめぐる共依存が成立する。その図式に誰もが短期的に幸福を得て、長期的には破綻する。
落ちたボールを取り扱うための四つの局面
こうした構図を乗り越えるためには、落ちたボールをめぐる新しい視点が必要になる。今回はその視点を「ケアの倫理」という分野から借りてみたい。
ここでいうケアとは、ケアワーカーが行うような介助のみを意味せず、もっと広義を指している。その意味は一般名詞におけるケア care と近い。
米国の政治学者J・C・トロントは、ケアという概念に「この世界を維持し、継続させ、そして修復するためになす、すべての活動」という定義を与えた。
広大な定義だが、ポイントは維持・継続・修復というワーディングである。それは変革や創造といった〝派手な仕事〟とは異なった領野にある。
またトロントはケアを「この世界の隅々に至るまできちんと動かそうとする努力」であり「ケアとは、(誰かの)必要を満たすもの」だと書いている。この部分はAさんの「チームが困りそうだったら、つい手を出してしまう」という発言とも呼応する。
このケアについての考え方は、ここまでみてきたボール拾いの話と重なる部分が大きい。それを確認した上で、トロントがケア活動を分析するために用意した「四つの局面」をもとに、ボール拾いを考えていきたい。 [2]
1 気にかかる Caring about
ケアの出発地点は、何かの問題が気にかかることからはじまる。ただこのフェイズにおいては、まだ対応は漠然としている。ある問題(あるいは落ちているボール)を気にかけている、気になっているという段階にある。
気になりつつ、見て見ぬふりをすることも大いにありえる。英語では「みなが気づいているけど、見て見ぬふりをしている問題」を指して elephant in the room (部屋の中のゾウ)という。いよいよ誰かが触れなければいけないという問題もあれば、そのまま何事もなく過ぎ去ってしまうこともある。
チームの方針によっては、声をあげた人、言い出しっぺがその仕事を引き受けざるを得ないケースもある。そういうチームでは、ボールはますます落ちたままになるだろう。
落ちているボールをいかにチームの関心事にするかが、この後の展開の鍵を握っている。
2 関心を抱く Caring for
第二の局面では、一歩進んで、その問題や仕事について関心を抱き、対処の方針を明確にする。担当者や日程を決めることも、この局面で行われる。
ボールを積極的に拾ってあふれてしまう人は、第一と第二の局面を混同してしまっている可能性がある。「四つの局面」においては、何かの問題が気にかかることと、それに対して具体的な対処を策定することは、べつの事柄なのだと定義されている。
職場においては、この局面で対処の主体が、個人からチームへと移行されるべきだろう。
3 ケアを提供する Caregiving
いよいよ実際にその仕事が遂行される。第三の局面においては、問題を解決するためのリソースが問題になる。
落ちたボールは、計画の外からやってくる「宣言されない仕事」なので、暗黙的に担当者が偏ることは好ましくない。もともとあった計画との整合性、優先順位も問題になる。
そして無事に提供が果たされた後にも、もう一つの局面が残っている。
4 ケアを受け取る Care-receiving
第四の局面は、ケアを受け取ることだ。問題が解決されたことを確認するとともに、落ちたボールを誰かが拾ったことによって、チーム全体が恩恵を受けたことを認識する。
感謝の言葉が表明されることもあるだろうし、仕事の大きさによっては、計画の修正、評価や査定にまで踏み込むときもあるだろう。
次にボールが落ちたときの対処方法や再発防止策を考え、状況を改善していくこともまた、この局面の役割である。この局面を通して、ケアをめぐる状況の全体が改善される。
以上の四つである。
この四つの区分は、落ちたボールに対する最適な対処法を与えるものではない。しかし、落ちたボールをめぐる三つの問題(対処した人が評価されないこと、優先順位を違えてしまうこと、チームがそこに依存してしまうこと)を考える上では有益なツールとなるだろう。
問題のあるチームではケアは誰かの独断によってなされ、他の人はそこに関心を持たず、誰もケアを受け取ることはない。四つの局面に沿ってチームの方針を振り返ることで、よりよい対処につながっていくはずだ。
人を助けることの尊さと危うさ
今回はボール拾いという行為を、ことさら大きく取り上げた。ただこの行為は、実際にはそれほど明確な輪郭をもたず、どこの職場にも日常的に存在している。
多くのチームでは、この記事で記したほど明確な「ボール拾い担当」がいるわけではないだろう。同僚への手助けは、多かれ少なかれみなが行っている。
オフィスの床に落ちてるゴミを捨てることや、日差しが差し込んだ窓のブラインドを下げることや、会議のあとにホワイトボードを消すことだって、ボール拾いの一つだ。そういうことは職場に限らず、日常生活の至るところにある。
ただその中でも、なんとなく多く拾う人と、少なく拾う人がいたりする。多く拾う人は、善意で行っているように見えて、そうせざるを得ない人たちだったりもする。
ありがたい役割を担ってくれている親切な人のように見えて、内心では苦しんでいるかもしれない。評価のギャップに苦しんだり、あるいはそれを居場所にしてしまっているかもしれない。周囲のメンバーも、そこに気づいていながら、見て見ぬふりをしているかもしれない。
本記事がそういう状況を見直すきっかけになればさいわいである。
ボールの対処にはいくつもの選択肢がある。明確に担当をつけ、お互いの納得の上に(つまり宣言した上で)仕事をしてもらうという道もあるだろうし、メンバーがローテーションで公平に分担するということもあるだろう。
いずれにせよ重要なのは、それが暗黙的に偏らないことだ。
落ちているボールの問題は、落ちているボールそのものにあるのではなく、その拾われ方にある。
暗黙的で自主的な手助けというのは美しく、人間関係を円滑にする最高の手立ての一つである。だからこそ、わたしたちはその尊さを知るのと同じくらい、危うさについても知っておかねばならない。
註
- [1] 「Ivan Illich『SHADOW – WORK』」
- [2] 「白澤社『ケアするのは誰か?: 新しい民主主義のかたちへ』ジョアン・C・トロント (著), 岡野 八代 (訳・著)」 より、見出しの訳は本記事の意図にあわせて改訳。