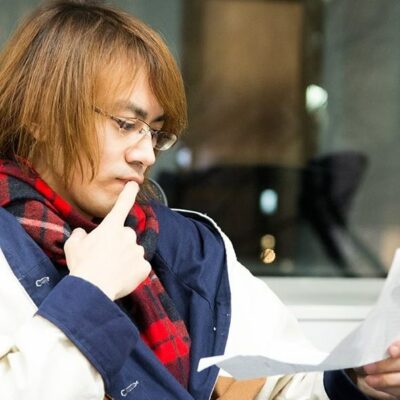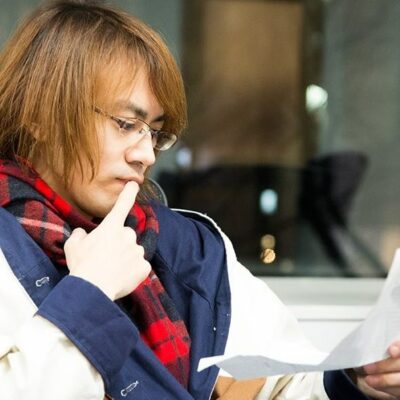「ぜんぶ自分の責任ですから」
そういう口癖の同僚がいた。責任感がつよかった。仕事に熱心で、管理職に就いて活躍していた。苦労を厭わない人で、人に厳しいところもあったが、他の誰よりも自分に一番厳しい人だった。
わたしは彼女のことを尊敬していたが、彼女がトラブルにあって「ぜんぶ自分の責任ですから」と苦く笑うとき、いつも哀しさと苛立ちの入り混じったような、複雑な感情を抱いていた。その言葉が彼女自身を雁字搦めにして、伸びやかな活躍を奪っているように感じられたからだ。
他責にするなとか、自責で考えようとか。そういう規範めいたフレーズがある。いっときに比べればすこし廃れてきたような気もするけれど、使われなくなったというほどでもない。多くのビジネス書や研修が他責的な振る舞いを非難し、かわりに自責で考えることを薦めてきた。
廃れたというよりも、風向きが変わってきたのかもしれない。メンタルヘルスが重視されてきたことによるのか、流行のバックラッシュなのか、自責思考の弊害を耳にすることが増えた。自責ばかりもよくないんじゃないの、という指摘がある。
中身はだいたいふたつに集約される。ひとつは自分に責任があると思いすぎてしまうことにより、精神が摩耗してしまう問題。もうひとつは起きている問題に対して、正しい責任追求や原因分析が阻害されてしまうという問題だ。
かわりに台頭してきたのは「健全な自責思考が大事」「自責と他責のバランスが大事」という言い方や、「自分には自責でいいが、他人に自責を求めてはいけない」という実利的なアプローチである。これらは一見、穏便な解決策に見える。
しかしわたしはこの方向性にも危うさを感じている。「健全な自責」や「バランスのよい他責」は存在しうるのだろうか。ほんとうに「自分には自責でいい」のだろうか。
自責や他責といった言葉の手触りを感じながら、わたしたちがどのようにこうした言葉に接してゆけばいいのかを考えたい。
まずは自責という言葉の副作用について今一度振り返ろう。違和感を持っていたという、リブセンス社員のひとりに話を聞いてみた。
「自責思考」の恩恵と副作用
「自責とか他責って、学生のときは知らなかったですね。社会人になってよく聞くようになりました」
人事部の五十嵐理紗さんは、二〇一七年に新卒でリブセンスに入社した。今から八年前になる。新人のころに社会人のマインドセットの一つとして教えられたという。
仕事がうまくいかないときに、どう考えればいいか。どう行動してゆけばいいか。その思考習慣の一つとして、自責思考を身につけた。
「自責で考えるということには、いい面もありました。なんでも自責で考えるくせがつくので、何か課題が起きたときに、自分ができることはなんだろうと考えられるようになって。恩恵を受けているほうが大きいと思っています」
そう前向きに語る。自責思考の問題点を指摘する人たちのなかでも、一定の擁護をする人は珍しくない。さきほどの「バランス派」もそうだった。
つづけて彼女は、その副作用についても語った。
「ただ、今思い返すと必要以上に自責で考えてしまうこともありました。本来考えなくていいところまで、無意識レベルで自責で考えちゃって。真面目な性格の人だと、鎖のようになるかもしれません」
この「無意識レベルで自責で考えてしまう」という発言は興味深い。
肯定的にみれば、彼女が自責思考を自身の内面深くまでインストールできたことを意味する。自然体でそう振る舞えるようになるのだから、自責思考を薦めるような本からすれば、立派な成功事例かもしれない。
しかし否定的にみれば、コントロールを失っているともいえる。それゆえに、彼女はそれを「鎖」と表現した。自分の考えによって、自分が縛られている。不自由になっているということだ。
社会には自分にはどうしようもないことが山ほどあるし、自分の責任範囲は限られている。自責思考は、それを乗り越えるように促す。うまく問題が解決できれば御の字だ。しかし乗り越えられない場合もある。そういうときの方が多いかもしれない。そんなとき、自責思考はきっと負い目を生み出してしまう。
インタビューの最後に、自分の後輩にも同じように自責思考を促すかどうかを聞いてみた。先ほど彼女は「恩恵を受けているほうが大きい」と言っていたから、同じように薦めるのかもしれない。しかし、返答は違っていた。
「薦めづらいと思います。よほど他責で考える人だったら言うかもしれない(笑) でも本人もある程度わかってそうなら、言わないですね。自責か他責かの線引きって人によって異なるので、そこが使いづらいなと思います。線引きは、その人の能力だったり経験してきたものによって違いますよね。本人はどうしようもないと思っていても、その問題の解決策が見える人から見たら、他責に見えちゃう気がするんです」
たしかにそうかもしれない。自責か他責かの線引きは、能力や経験によって異なっている。
彼女の発言が納得を生じさせる一方で、それを飲み込むかわりにひとつの当惑が浮上する。もし本当に線引きができないのだとしたら、わたしたちが使っている自責や他責という言葉は、根本的な欠陥を抱えているのではないか。
自責や他責という言葉の由来
ここまで当たり前に自責や他責という言葉を使ってきたが、この章ではあらためてこれらの言葉そのものについて、意味や成り立ちを考えてみたい。
なぜそんな面倒なことをするのかというと、自責や他責という言葉がふつうの言葉ではないからだ。
辞書を引くと気づく。これらの言葉は、辞書通りの意味で使われていない。というか、他責にいたっては、そもそも辞書に掲載されていない。自責は掲載されているものの、その意味は捻じ曲がっている。
むろん、辞書が絶対的に正しいわけではない。言葉は変わりつづけていて、辞書は現実を追いかけるだけだ。しかし、伝統的な意味があるにも関わらず、それとは異なった意図で言葉を用いるなら、意味の受け取られ方は人によってバラバラになるだろう。そこにすれ違いや副作用も現れる。
昔から自責という言葉は、あるにはある。
よく知られる慣用句に「自責の念」がある。自分で自分を責めてしまうことを「自責の念に駆られる」という。国語辞書でも「自責」の項では「自分で自身のあやまちを責めとがめること」と記載されている
[1]
。今日の自責思考の意味とは、少しズレている。
自身のミスや失敗が前提となっていて、それを悔やんだり惜しんだりすることが本来の自責である。あれもこれも自分ごととして考え行動することが自責であるという、現代のビジネスシーンの用法とは異なっている。
新しい意味も徐々に用例が増えてきたからか、新語の掲載に盛んな辞書では掲載例がある。先ほどの「自分を責める」という記述に加えて「また、自分に責任があると考えること」と付け加えられている
[2]
。「また」という接続詞に表れているように、似ているようで別の意味だ。自責はいつの間にか、二つの意味を持つ言葉になった。
他責のほうは先述したように、そもそも多くの辞書に載っていない。近年のビジネスシーンが突然に懐胎した言葉らしい。
発祥は定かではないが、大きく広まったのは九〇年代からゼロ年代のようだ
[3]
。特に九九年に日産のCOOにカルロス・ゴーンが就任して改革を打ち出したときには、日産の問題点として「他責文化」という表現がよく使われていた。
その後、たとえば〇四年にはリーダーシップ教育で名を馳せる野田智義氏が、ビジネス誌において他責文化を「日本の悪しき風習」だと断罪し、「『いま自分は何ができるか』という前向きな自責の姿勢」へと変化するよう促している
[4]
。この頃から「他責よりも自責」というスタンスが明確になっていったようだ。
一〇年代には「自責社員と他責社員」や「成功する企業に共通する『自責』のルール」と題した本が相次いで発売され、この流れは決定的なものとなった。
つまり、自責も他責もここ三〇年ほどで急に台頭してきた目新しい言葉だったのである。ではなぜ九〇年代からこのような言葉が使われはじめたのだろうか。その背景を探ってみたい。
- [1] じ‐せき【自責】, 日本国語大辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2025-07-25)
- [2] じ‐せき【自責】, デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2025-07-25)
- [3] 「他責」という言葉を確認できたもっとも古い文献に「他責の念と自責の心」(増田義一『今後の進み方』実業之日本社、1937年、140-153頁)がある。ここでは他責と自責が対比的に用いられ、他責から自責への転換が促されている。ちなみに増田は政治家や出版業を務め、大日本印刷の初代社長にもなった人物である。
- [4] 野田智義「『行動しないミドルが生まれる』組織学」『PRESIDENT』プレジデント社、2004年3月15日号、50-55頁
自責=自己責任?
なぜ自責・他責という言葉が、ここ三十年で急速に広まったのか。結論からいえば、わたしはこの背後に自己責任論の流行を見ている。そこで、自責と自己責任のつながりを見ていきたい。
自責思考にはふしぎな点が一つある。もしすべてを自分ごとに帰せるというのなら、チームの成功や周囲の達成も自分のおかげだと解釈できるはずである。成功も失敗も自分ごととして味わえるなら、それはそれでいいかもしれない。
しかし自責思考は、そういうふうには作用しない。自責思考はネガティブな側面ばかりを引き受けるのである。なぜだろうか。
その糸口は、自責の「責」という字にある。
「責」は「責める」という意味である。本来の自責がそうだった。自分で自分を責めてしまうのが自責である。「責」という字は負のニュアンスをつよく想起させる。自責という言葉には、どうしてもそういうイメージがつきまとっている。
いくら著名人がビジネス誌で「自責思考とは、いま自分は何ができるかという前向きな姿勢」なのだと言ったところで、わたしたちが連綿と受け継いできた語のイメージを、あっさりと上書きすることはできない。言葉には、その言葉が使われてきた歴史が宿っている。
自責とよく似た言葉に、自己責任がある。自責という言葉自体は何かの略語ではないが、自責と自己責任というふたつの言葉を並べたとき、両者はとてもよく似ている。またその類似性は、字面だけでなく歴史についても当てはまる。
自己責任という言葉も、九〇年代から広まりはじめた。バブル崩壊後の不安定な情勢を受けて、大企業と終身雇用の神話が終わりを告げ、個人で生き抜く時代が始まった。自己責任は、そういう時代のど真ん中から生まれてきた言葉だった。
ゼロ年代には経済以外の文脈でも使われるようになり、〇四年にはユーキャン・流⾏語⼤賞のトップテンにランクインしている。ただ当時の状況を見るに、そこには「自業自得」を言い換えたような冷たさがあった。
自責と自己責任は違う言葉ではある。しかし見た目も歴史も似通ったこの二つの語は、どこか共通のイメージを抱えていて、自責という言葉にも自己責任の冷たさは伝わっているように思う。
冒頭に記した「ぜんぶ自分の責任ですから」という言葉のやるせなさも、自責と自己責任の同一化からきている。
押し付けられた責任と本来の責任
自責や他責といったビジネス用語がここ三〇年の間に出てきたものであること、そしてその背後には自己責任論の興隆があったことを見てきた。さいごに、これらの言葉の核を担っている「責任」というものに迫ってゆきたい。
まずは、その鍵となるひとつのフレーズを紹介しよう。
「押し付けられた責任だけを、僕らは責任と呼んでいる」 [5]
そう言ったのは哲学者の國分功一郎だった。
どういうことなのか。責任という概念の前提から考えてみたい。
責任が発生するのはどんなときか。それは自身が何かしらの選択を誤ったときだ。たとえばお酒を飲んで運転したら罰せられるのは、お酒を飲まないことや運転しないことも選択できたからだ。物を盗んで罪に問われるのは、購入することを避けて、盗むことを選んだからだ。
つまり責任は、個々人の選択を、おおげさに言えば個々人の自由意志を前提としている。わたしたちが自らの意思によってその行動を選択したからこそ、結果に責任が伴っている。
こう書いてみると、まともな理屈に見える。しかし國分は、この自由意志と責任の関係に疑念を呈する。
場面を仕事に戻してみよう。あなたがミスや失敗を引き起こしてしまったとする。そうするとあなたが、その責任を担うこととなる。
しかしとうぜんそれは、意図されたものではない。前向きな結果を求めて動いた結果、そうなってしまったのだ。失敗はいつも偶然である。
それでも失敗した途端に、状況は一変する。この失敗はあなたが引き起こしたものですよね、と言われて、そこに見たこともない責任が出来する。
責任はあらかじめ存在していたわけではない。問題が先に誕生すれば、責任はそこに後からやってきて、責めていい相手を探しまわる。だから責任は「押し付けられた責任」というわけだ。國分はこれを「意志の概念によって主体に行為が帰属させられている」
[6]
と説明する。
言い換えれば、責任とは一定の決められたサイズで、あらかじめそこに置いてあるものではない。自責や他責は、その塊を切り出してやりとりしているのではない。
責任とは、誰かが押し付けたり引き受けたりするまさにその瞬間に、蛇口を捻って水が出てくるように、際限なく生まれてくる。そこには歯止めがない。
自責や他責は、責任をコントロール可能なものとして扱う。これがそもそもの過ちだった。責任は制御できるような対象ではない。押し付けようとすればいくらでも押し付けられ、引き受けようとすればいくらでも引き受けてしまえるものだ。
誰かがミスをしたとき、それは本人の注意不足なのか。業務マニュアルの記述が悪いのか。いやいや上司の監督の問題なのか。育成がなっていなかったのか。そもそも採用が間違っていたのか。と、責任はいくらでも増量できてしまう。これが自責思考の根本的な危うさである。
補足しておくと、國分は責任という概念のすべてを否定しているわけではない。責任感の重要性を否定しているわけではない。人が目の前の問題に直面したとき、誰に言われずとも、自分が何かすべきだと自ずと決意するときがある。そういう義の心こそが、本来の責任なのだと説いている。
それに対して、自責や他責といった言葉は、責任を自在に動かせるものとして扱う。それは人が自ずと感じたはずの、本来の責任感を損なってしまうことにすらつながってしまうだろう。
- [5] 國分功一郎、熊谷晋一郎『<責任>の生成 中動態と当事者研究』新曜社、2020年、119頁
- [6] 同書、116頁
「健全な自責」の難しさ
今一度、五十嵐さんの言葉を思い出そう。彼女は「必要以上に自責で考えてしまうこともありました」と言っていた。
このときに意味していたことは、とうぜん、必要以上に前向きな姿勢を持ったということではない。必要以上に主体的に仕事に取り組んだということでもない。必要以上に自分を責めてしまっていた、ということだ。自責思考はどこかで自己責任論に、そして自罰感情につながっている。
だから、「バランスのよい自責」や「健全な自責」という物言いは危うさを抱え続ける。
他責や無責任がいいと言いたいわけではない。過剰な他責傾向に問題があるのは明らかだ。しかし自責を薦めればバランスがとれるわけではない。他責も自責も、どちらにも問題がある。それは責任を自在に動かせるものとして捉える見方の問題だ。
他責を戒めようと自責を促せば、意図するかどうかにかかわらず、自罰感情を呼び起こしてしまうことがある。自責という言い方には、そういう副作用がある。
特に新卒には、こういう教育が多いのかもしれない。今年の春もどこかの会社で、他責になるな自責であれと指導があったのだろう。そこには恩恵もあったかもしれない。建設的に議論することや、主体的に行動することはたしかに大事なことだ。
ただ、それらを自責と言い表す必要があるだろうか。自責の鎖につながれた人々に思いを馳せながら、この言葉の手触りをあらためて感じたい。