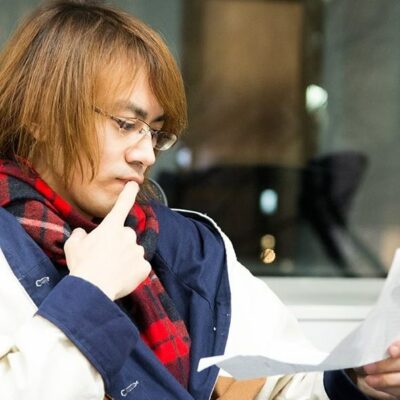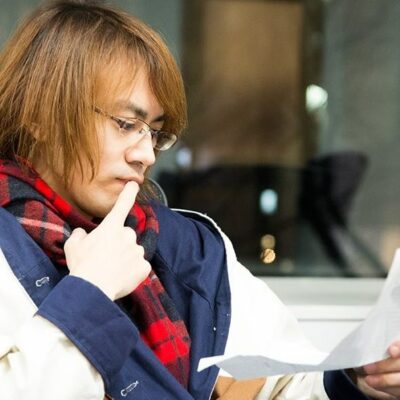はじめに、短いフィクションをご覧いただきたい。
ある会社で、事業部長のAさんが育児休業をとった。Aさんはその事業を成功へと導いてきた立役者で、経営陣も部下もAさんのことを信頼していた。そんなAさんが育休を取ることになった。まずは一年間の予定で、Aさんがその間不在となるので、会社はべつの人を事業部長として立てることになった。
新しく事業部長に登用されたBさんは、Aさんのもとで副事業部長を務めていた。事業部長には時期尚早だと思われていたが、Aさんの育休がきっかけとなって抜擢された。臨時の登板とはいえ、一年間は短くない。もともと事業部長を目指していたBさんにとっては、絶好の機会だった。
事業部はBさん体制のもとで、再編成されることになった。副のポストが空いたので、新たな副事業部長も登用され、組織の若返りも起きた。Aさん体制は素晴らしかったが、Bさん体制もなかなかだった。
事業部が傾いてはAさんが安心して家庭や育児に専念できないだろうと、一同が奮闘した。Bさんもトップの仕事に邁進し、半年が過ぎたあたりからは、Aさんの穴を感じさせなくなっていた。
Aさんは保育所への入所がうまくいかず、育休を延長することになった。結果、一年延長し、都合二年休むことになった。その間に、Bさん体制は新たな幹部も採用し、メンバーも増え、ますます盤石になっていった。気づけばAさん体制に負けず劣らず、いい組織になった。Bさんも部員も、すっかり新事業部としての自信を持っていた。この組織でずっとやっていきたいと思うようになった。
二年間の育休の満期が近づいたとき、Aさんは会社に連絡を入れた。
「そろそろ復職の時期になりました。また事業部長として腕を振るえるのを楽しみにしています」
どちらが事業部長になるべきか
さて、あなたはこの会社で、人事を左右する立場にいるとしよう。目の前には悩ましい二者択一が横たわっている。Aさんを事業部長に戻すのか、Bさん体制のままでいくのか。どのように判断するだろうか。
あなたはBさんを事業部長のままにしておきたい、と思うかもしれない。新たなチームが一丸となって二年が経過したいま、Aさんの返り咲きは、必ずしも喜ばしい出来事ではない。
Aさんを事業部長に戻すとしたら、Bさんはどのように処遇すればいいだろう。副に戻すのか、他の部署に異動させるのか。
二年間、事業部長としての職務をまっとうしたBさんを異動させる理由は見当たらない。Aさんを事業部長に戻しBさんを職位から外すことは、BさんやBさんを慕う部下のモチベーションを下げ、離職を招いてしまうかもしれない。
それよりは、Bさんを事業部長のままにして、Aさんの異動先を探す方がスムーズだ。
Bさん体制を変えない場合、何が起きるだろうか。
あなたはAさんの配置を考えなければならない。たまたま他に、Aさんの能力にぴったりで待遇も変わらない役職があれば、ラッキーかもしれない。ただしそうだとしても、Aさんは愛着の深い事業部を離れることになる。
もし、そういう都合のいいポジションがなければ、Aさんの職位を外す必要があるだろう。Bさんの下か、べつの事業部に入ってもらうことになる。
それは、Aさんが育休を取ったことによって降格してしまうことを意味する。
Bさん体制の頑張りを考えれば、Aさんの異動はやむを得ないことかもしれない。しかし、今後その会社では、管理職は育休を取りづらくなるだろう。
育休を取れば、職位を失う。たとえそこに納得せざるを得ない合理性があったとしても、職位や裁量をやりがいとする人たちにとっては、あまりに厳しい裁定である。
この話はフィクションだ。ただこんなことは今どんな職場でも起こっているし、管理職の長期の育休が増えていけば、今後いくらでも増えていくだろう。
どちらを選ぶべきかに、正解はない。本人たちの意向や、組織の状況にもよる。しかし考えるにあたって、いくつかの補助線はある。
降格を阻む法律の壁
先ほど書かなかった重要な事実が一つある。Aさんの降格は、法律に抵触する可能性が高いということだ。
日本では「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」において、結婚・妊娠・出産・産休・育休をきっかけにした「不利益な取扱い」を禁止している。
どんなものが「不利益な取り扱い」に該当するかは、厚生労働省が指針を示しているので、一部を抜粋する。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- 降格させること
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
ここで明示されているように、育休をきっかけとした降格は、違法となる可能性が高い。降格と減給がべつべつに明記されていることから、たとえ給与が変わらないとしても、降格は禁止されていると読みとれる。
本人が降格に納得している場合はどうだろうか。
一昔前までは、多くの会社が、本人が納得していれば問題ないはずだというスタンスをとっていた。
Aさんには事業部の現状や、他の部長ポジションも空いていないことを丁寧に説明する。Aさんも快諾というわけではないが、会社の事情を慮って降格を飲む。
いかに法律が「不利益な取扱い」を禁止しているといっても、違法となるのは本人の反対を押し切って会社が断行した場合であって、本人との合意が取れていれば問題ないはずだ。そういう考えが多くあった。
しかし二〇一四年に、事態は一変する。
まさにこうした降格をめぐる裁判で、最高裁が「本人が受け入れていたとしても、それだけで適法とは言えない」と判断したのだ。
先のフィクションとちがって、少し事情は込み入っているが、問題の核心は似ている。ある女性が妊娠をきっかけに役職を降り、育休からの復職時にも役職に戻らなかったことで、会社に不服を申し立てたものだ。
この事件が注目された一つの要因は、当人が役職を降りることについて、同意していた点にある。
女性は妊娠をきっかけに身体への負担が小さい仕事へと移り、そのときに役職も降りた。その後に育休に入り、復職。復職後も役職へは復帰できなかった。
育休後に役職に復帰しないのは適法か、違法か。一審と二審では降格は適法とされていたものが、最高裁でひっくり返った。
最高裁は、降格を原則的に違法とした上で、二つの例外を提示した。判決を受けて厚生労働省もこの例外を指針に加え、それが今日まで続いている。
降格が適法となる二つの例外
「不利益な取扱い」が適法となる例外は二つある。ざっくり要約すると、ひとつ目は「誰でも同意するような理由があればOK」、ふたつ目は「特段の事情があるときはやむなし」というものになっている。
実際の文面はこのようなものだ。
- 不利な影響を有利な影響が上回り、一般的な労働者であれば当該取扱いに同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき
- 法の趣旨に反しないと認められるほどに、不利益を上回る特段の事情が存在するとき
ひとつ目は、章で触れた「同意」についてのものだ。「一般的」「合理的」「客観的」といったワードが並んでいることに注目されたい。
同意は確かに、例外ケースの一つとなっている。しかしその条件は極めて厳しい。単純に本人が同意すればOKとはなっていない。
本人だけでなく、誰であっても(「一般的な労働者」であれば!)合意するのが当然だろうと思われる「有利な影響」がある場合にのみ、この合意は有効となっている。たとえば本人が業務量の軽減を要求し、会社側がそれに応じる形で降格に同意するようなケースがこれに含まれる。それはもはや不利益とは言えないから抵触しないよ、という理屈だ。
だから、育休に入る人が渋々承諾したようなときは、当然この例外には含まれない。
例外のふたつ目は「特段の事情」というものだ。この「特段の事情」は、業務上やむを得ない場合に限定されている。
たとえば会社の赤字が続いているとか、債務超過であるとか、そういうことが想定されている。「替わりの部長がいるから」では通らない。
本人の能力不足を理由にすることもできるが、これも条件はかなり厳しい。妊娠等が起こる前から能力不足を問題にしていたこと、改善の機会が相当程度与えられていることなどが要件になっている。要するに、育休取得に関わらず降格が予定されていた場合に限る、ということだ。
このふたつは「例外」と言われるだけあって、極めてハードルの高いものだ。もともと法律が禁止しているものを通すためのハードルだから、高いのは当然といえば当然だけど、なかなか現実的に適用するのは難しそうに見える。
では結局のところ、先の例ではAさんを事業部長に戻すしかないのだろうか。リブセンス社内でも二人に意見を聞いてみた。
当事者の声、人事の声
ヒアリングのひとり目は元当事者の斉藤右弥さん。部長職から育休に入ったことがあり、そのときは一年間の育休をとっていた。
「育休に入るときに、替わりの人が立つことについては話しました。復職後は元の役職に戻ることが多いと思いますが、ではその間に就いた人は穴埋め要員なのかって話ですよね……難しいですね。正直ぼく自身は役職にこだわりがなかったので、当時はそこまで考えなかったです」
斉藤さんのケースでは上長が兼務する形で育休期間を乗り切ったので、どちらを部長にするかの二者択一は発生しなかった。しかし斉藤さん自身も、こうしたジレンマには頭を抱える。
「会社としてはフラットに見た上で、新部長と比較して決めたいですよね。その結果に納得性があればやむを得ないですし。正直、〝後任の人がうまくいってるけど、戻さざるを得ないから戻しますよ〟は復職する側も気持ち悪い気がします」
確かにそれが理想的な判断かもしれない。しかしこうした判断が、真にフラットかどうかを判定するのはとても難しい。
労務の伊藤愛美さんも、まずは、こうした方向性に賛同している。
「能力や成果創出に応じた登用・配置転換は、人事権の行使として当然に行われるものです。ですから、後任と比較して役務遂行能力が勝る場合は戻す、そうでなければ後任がそのまま継続という判断であれば、通常の人事異動の範囲として、許容されると思います」
筋の通った考え方だ。その一方で、労働判例にも目を通している伊藤さんは、法律が課す要件の厳しさについても、強い懸念も示していた。
「しかし、それであっても不利益取扱いとされる可能性は残ります。法への抵触を避けようとすると、前任者を元に戻す方向が無難という考えになるのではと思いました。個人的には、そうした判断が後任に対する逆差別になる可能性も感じます」
会社としてはリスクを避ける方向に力学が働くが、本当にそれでいいのだろうか。葛藤がうかがえる。
このジレンマは何を意味するのか
突きつけられた問題は明白だ。役職者が休業期間に入り、替わりに誰かを立てるなら、復帰したときには、どちらかが降格にならざるを得ない。そして降格に伴う要件は、あまりに厳しい。
どう考えてもこれは行き詰まっている。しかし何が行き詰まっているのだろうか。
法の趣旨が悪いわけではない。育休をとる社員がキャリア上の不利益を被るような社会は、当人たちにとって望ましくないのはもちろんのこと、日本の未来をいっそう暗くするものだ。産休や育休を取得する人たちに、不利益があっていいはずがない。
しかし役職についても、それを厳格に適用していいのかは、一考の余地があるように思う。企業における役職は、第一にそれぞれの組織における役割であって、個々人の能力の証明ではないからだ。
厚労省は「不利益な取扱い」における降格の定義について、以下のように示している。
同格の役職間の異動であれば、異動先の役職の権限等が異動前の役職の権限等よりも少ないものであったとしても、「降格」には含まれない
この文言を読めば明らかなように、法律上の争点になっているのは、役職の「格」そのものだ。
それくらい裁判所や厚労省は「降格」それ自体を重くみなしている。しかしポジションは限られた数しかないのだから、誰かが降格にならざるを得ない。
[1]
このジレンマが示すのは、昇格を良しとし、降格を悪しきものとするキャリア志向そのものの限界である。
役職で人を評価したり、役職によって自分の価値を裏付けたくなるのを、どこかでやめなければ、このジレンマは解消されない。
もちろんそれは簡単ではない。たとえば転職のときに、役職がまっさきに評価されるのであれば、人々は役職に固執せざるを得ないだろう。名刺交換のときに役職で相手を見定める習慣があれば、役職にこだわりたくもなるだろう。そういう個々人の生存戦略を、誰も非難することはできない。
それでも限界はすぐそこまできている。今日もどこかの会社で、こうしたジレンマが起きている。
出口のない過渡期の中で
役職を重視しない新しいキャリア観も、目にしなくはない。
組織論やキャリア論で知られるリンダ・グラットンが、著書『ワーク・シフト』でカリヨン・ツリー型のキャリアを提示したのは、今から十年以上も前のことだった。カリヨン・ツリーとは鐘がいくつも吊るされたぶどうのような楽器で、非線形的・多角的なキャリアを表している。
新しい専門分野に精力的に取り組んで技能を高める時期、仕事のペースを緩めて自分の人生についてじっくり考える時期、仕事を中断して勉強に専念する時期、ボランティア活動に集中的に携わる時期──こうしたさまざまな時期がモザイク状に入り組むのがカリヨン・ツリー型のキャリアだ。
ただ、ここ十年でこうした選択がどれほど現実的なものになったかといえば、残念ながら疑わしい。グラットンの提唱するキャリア観は、まだまだ一部の限られた人たちのものに過ぎない。
単線型キャリアが限界を迎えていることには、みんな薄々気がついている。その限界は育休に限らず、病気や介護といったケースでも露呈するだろう。役職が右肩上がりで上がり続けるキャリアを理想とすべき時代は、そろそろ終わりにした方がいい。
しかし次のキャリア観への移行へはまだ時間がかかりそうだ。もしくはずっと起こらないのかもしれない。その間、この社会は誰かの痛みを抱え続ける。
こうした局面で、わたしたちが採るべき正解は存在しない。育休に入る人も、替わりに登用された人も、この問題を取り扱う人事も、みな悩ましさを抱え続ける。こうした苦難をみなが抱えていることくらいは、せめて知られていて欲しい。