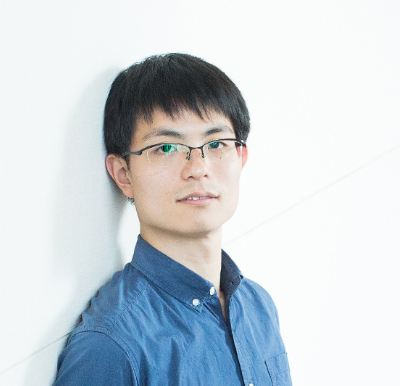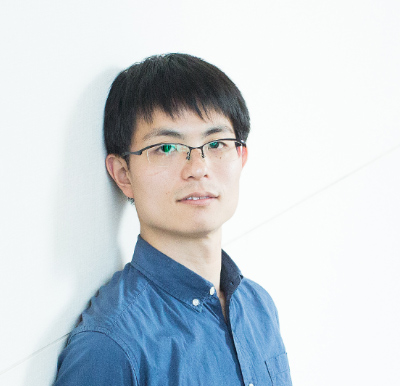みなさんは、自分が日々携わっている仕事について、その背景や文脈をどこまで理解しているだろうか。
あまり考えたことがない人から、誰よりも真剣に向き合っていると胸を張る人までさまざまだろう。どちらが良いか悪いかはいったん置いて、個人的な経験から思うことは、そこまで深く理解していなくても案外仕事は回るということだ。
これだけ言うと怒られそうな気もするが、ちょっと待ってほしい。イソップ寓話の「三人のレンガ職人」の話をご存じだろうか。簡単に紹介すると、旅人がある町でレンガ積みをしている三人の男に出会う話だ。
旅人はレンガ積みという同じ仕事をしている三人それぞれに「ここで何をしているのか?」と尋ねると、一人目の男は「見れば分かるだろ。レンガを積んでいるんだ。暑い日も寒い日も朝から晩までこんな大変なことをやらないといけないんだ」と嘆いた。二人目は「大きな壁を作っているんだ。この仕事があるから俺は家族を養っていけるんだ。大変だなんて言ったらバチがあたるよ」と答えた。三人目は「この場所に、歴史に残る偉大な聖堂を作っているんだ。将来、多くの人がここで祝福を受け、そして悲しみを払うんだ。素晴らしいだろう!」と誇った。
要するに、やっていることは同じでも考え方や捉え方次第で見える世界は全く異なるという話だ。一方で、何のためにその仕事をしているのか理解していなくとも仕事自体はできるという捉え方もできる。
今回のテーマは、年次有給休暇(以下、有給)はなぜ毎年付与される日数が増えるのかということだ。
私はこれまで七年ほど労務の仕事に携わってきて、有給付与の仕事も行ってきた。仕事がら制度の仕組みそのものは頑張って覚えたが、その背景に思いを馳せることはこれまでなかった。だから、Q by Livesenseの編集会議で「有給ってなんで増えるんですか?」と聞かれたときに答えることができなかった。
そこで、年次有給休暇とはそもそもなんなのか、それはなぜ毎年増えるのかを改めて考えてみたい。
有給のあれこれ
そもそも有給とはなにか。厚生労働省のホームページにはこう書かれている。
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
「有給を取った日は働かなくても給与が支払われる」というのは一般的にも認知されているであろう。一方で、それ以上のこととなると往々にして誤解もつきまとう。
そもそも有給は雇用形態や会社の業種・規模に関係なく付与される。したがって、たとえば週一日勤務のアルバイトであっても要件を満たしていれば付与されるし、会社が就業規則で有給を定めているか否かも関係なく取得できる。ただし、フリーランスなど業務委託として働いている場合は労働基準法が適用されないため有給も付与されない。
また、有給を取る際にその理由は問われない。理由を尋ねること自体は問題ないし事業運営に支障が出る場合に取得日を変更することは可能だが、理由の内容によって取得可否を決める権利は会社にはない。できるかぎり前もって申請しておくなど一定のモラルや周囲への配慮は必要だが、前日に思い立って旅行に行こうが、所用で役所に行こうが、あるいは何もせずに家で無為に過ごそうが問題ない。
世の中では、有給が「きちんと」付与されることや理由を会社に申告せずに取得できることを以って「クリーンでホワイトな会社」としてアピールする事例も時折見かけるが、本来それらは当然のことであり、逆にこれまでの社会の悪しき雇用習慣の根深さを感じさせる。
次に、有給がいつどれくらい付与されるのか見ていきたい。
まず、入社後六ヶ月経過した時点でそれまでに八割以上出勤していることを要件として、十日付与される。そのあとは一年に一回付与され、日数は徐々に増えていき、最終的に一回で二十日分が付与される。ただし、たとえば週四日勤務だと入社して六か月後に付与されるのが七日になるなど、一週間の勤務日数および時間が一定の水準を下回る場合は付与日数は少なくなる。
なお、これは最低限のラインを法律で定めたものであり、会社の判断でより早くあるいは多く付与しても差し支えない。入社と同時に有給を付与する会社も多く、リブセンスでも無期雇用の場合は入社日に十日付与される。
ここでいくつか疑問が浮かぶ。有給が付与されるために、なぜ最初の付与まで六ヶ月の期間があるのか、八割以上の出勤が求められるのか、そして付与日数は徐々に増えていくのか。
これらの疑問を一言でまとめると「権利であるはずの有給が、なぜ会社への貢献の見返りとして与えられるのか」ということだ。
権利と義務はセットで語られることが多い。すなわち、義務を果たして初めて権利が発生する、裏を返せば義務を果たさない者には権利がないと考えられがちだ。しかし、権利は義務の対価ではない。厳密に言えば、権利とは自らに課される義務の対価ではなく、自らの権利行使にあたり第三者がなんらかの義務を負うという、他者との関係性を意味する。
そう考えると、有給は「権利」とは言いつつどこか零れ落ちてしまっている部分があると感じる。どうしてこのような仕組みになってしまったのだろうか。
有給はどのように成立してきたか
有給が成立してきた歴史的な経緯を概観すると、一九三六年にILO(国際労働機関)で一年継続勤務した労働者に対して六労働日以上の有給を勤務期間に応じて付与すること、そのうち六日は一括で付与すべきこと、付与日数は勤務期間に応じて増加すべきことを謳った「年次有給休暇に関する条約」(52号条約)が採択されている。
ここで注目すべきは、この条約では有給はまとめて一気に取ることが基本となっている点だ。日本では一日ごとに取得することが一般的で、一週間まとめて取得することを俗に「ぶちぬき」と呼ぶこともあるが、逆に「ぶちぬき」こそが本来的な有給の取り方であると言える。そもそもの有給の主旨が心身の回復であることを考えてもその方が自然だ。
52号条約を踏まえて各国で有給に関する制度の立法が進められた。
日本では戦後に法的整備が行われたが、52号条約の主旨とは異なり一日単位での取得を可能とし、かつ前年度に八割以上出勤することを権利取得の要件とした。その背景には、終戦後の労働者は生活物資確保のために週休以外にも休日が必要だったこと、また一般的に労働意欲が低下していた実情があったとされている。この結果、日本における有給制度は一定期間の継続勤務に対する見返りであり、また一日ごとの休暇という性格を帯びることになった。
ILOでは一九七〇年に、休暇日数は六ヶ月継続勤務した労働者に対して三労働週とすること、三労働週のうち少なくとも二労働週は一括付与すべきことなどを謳った132号条約に改正されたが、日本においては長く続いた雇用慣行を変えることが困難だったのか、細かい制度改定は重ねられてきたものの、有給の基本的な性格は今日まで変わっていない。
欧米諸国ではバカンスの名の下に長期休暇を取ることが一般的で、かたや日本では有給取得率を上げることが国の課題となっているが、どちらも元を辿れば九〇年近く前の条約に行きつくのだ。
そして、さきほど浮かんだ疑問について分かった部分もある。八割以上の出勤が求められるのは、戦後の日本の状況もありつつ現在はやや惰性的に続いていること。最初の付与まで六ヶ月かかることや日数が漸増していくことは国際的な条約に端を発していること。その文言が定められた背景までは今回はリサーチできなかったが、ただやっぱり権利とは言いつつ見返りとしての側面も否めないと言えそうだ。
知ることは、見える世界を広げること
有給休暇について調べてみたことで、自分の仕事を「そういうもの」としてある種受け流していたことに気づいた。
そして、知ったことで自分の何が変わったのか。表面的には正直変わっていない。冒頭でレンガ職人の寓話に触れたが、知ったところで今日明日私の仕事が変わる訳ではない。
一方で、内面的な変化はあった。まず、単純に自分の仕事に対する理解が深まったことでおもしろみが増した。
より疑問が深まった部分もある。たとえば、なぜ日本では有給の取得率が上がらないのか。これは想像の域を超えないが、権利というものに対する日本人の意識が関わっているのではないか。つまり、権利は無条件に行使してよいものではなく、義務を伴うどこかに負い目があるものという意識が通底しているのではないか。そういった可能性にも考えが及ぶようになり、自分の見える世界が少しだけ広くなった気がした。
世の中は複雑で、全てを理解しようとすると物事は前に進まない。だから、わたしたちは多かれ少なかれ思考を端折って日々を営んでいる。それ自体は悪いことではない。ただ、それの副作用として、物事はネガティブな側面も含めて現状維持されアップデートされない。だから、ときどき立ち止まって「あれ、これってなんでこうなっているんだっけ?」と考えてみることは、自分のためにも大切だと言えそうだ。