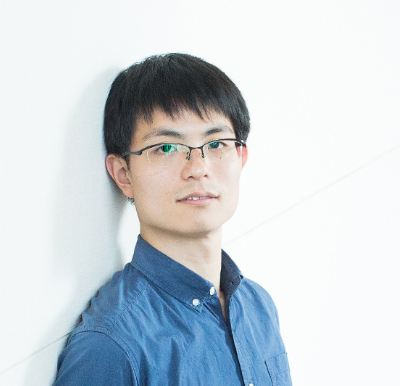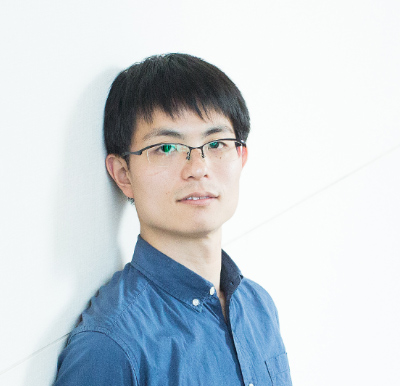「お疲れ様です……娘の体調が安定せず、本日は早退させていただきます。いつも申し訳ありません。よろしくお願いいたします」
これは、ある従業員からの勤怠連絡だ。連絡したのは2歳の子どもを持つ女性社員。時短勤務の制度を利用し、現在は1日7時間働いている。子どもが体調を崩して早退したり休まなければならなかったりするときは、こうした連絡をしている。
「いつも」と書かれているように、今回が初めてのことではない。だが、私も小さな子どもが二人いて、保育園の送り迎えなどで早退することがよくあるので気持ちは分かる。「お互い様だからそんなに気にしなくても良いのに」と感じたのが率直なところだ。
みなさんはこの連絡を見てどう感じただろうか。育児や家族の介護をしながら働いている人、あるいはそういう人と一緒に働いている人であれば、同じような場面に遭遇した人も多いのではないか。
一見、一人の従業員のなにげない連絡に見えるが、制度を利用できる人とできない人の間に対立構造を生み出しやすいという時短勤務制度が抱える課題が隠れている。これは、一個人の問題ではなく企業、ひいては社会の問題であることを紐解いていきたい。
日本と世界の時短勤務制度
日本では、1日の所定労働時間は8時間程度という企業が多い。そこに加えて多かれ少なかれ時間外労働を恒常的にしている人も多いだろう。育児や家族の介護をしている人にとっては、それだけの長時間働くことはどうしても難しい側面がある。そうすると、仕事と家庭のどちらかを選択しなければならず、仕事を諦めて退職せざるをえないケースも出てくる。
そういった事態を防ぎ、育児や介護をしながら仕事が続けられるように法律で定められているのが時短勤務制度だ。具体的には、育児・介護休業法において3歳未満の子どもを育てる社員に関して、1日の所定労働時間を6時間とする制度を設けなければならない。
もともと、育児・介護休業法ができた背景には「一・五七ショック」がある。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率(理論上はこの数値が2以上でないと、国の人口が減っていくことになる)が、統計を取り始めた一九四七年は4・54だったものが、一九八九年に当時過去最低の1・57まで低下した事態を指す言葉だ。そうした社会背景を踏まえて、少子化対策として女性が働きながら育児ができる環境を整えることを目的に、育児休業法が一九九一年に制定された。その後、高齢化社会に対応するための介護休業の仕組みや、看護休暇、時短勤務制度の創設など、何度か法改正が重ねられ現在に至っている。
海外にも目を向けてみよう。イギリスでは、特定の条件を満たす従業員が柔軟な働き方の権利を主張できるフレキシブル・ワーキング法がある。具体的には、子どもの登校時間に合わせて労働時間を短縮できる学期間労働時間制や、日本でも法制度があるフレックスタイム制、個々人に応じた始業時間や終業時間で働くことができる時間差勤務制などがある。
ドイツでは、在籍期間が6か月を超える社員全員を対象とした時短勤務の制度が法律で定められている他、フレックスタイム制やジョブシェアリングなど、数多くのフレキシブルな働き方のモデルが法律で提示され、会社ごとに制度を導入している。
アメリカでは、フレキシブルな働き方に関する国全体での法制度は少なく、それぞれの企業ごとに委ねられている部分が大きい。州によっては一定期間以上継続して同じ企業に務める社員が育児や介護をしやすいように、企業に対して支援を求める条例が制定されている。また、シリコンバレーなどのスタートアップ企業では、働く場所も時間も全て自由という働き方を導入している企業も見られる。
このように見ると、日本の法制度はアメリカよりもイギリスやドイツに近く、国としてのサポートは比較的手厚いと言える。
時短勤務制度の課題
もちろん、仕事とプライベートが両立できることはすばらしい。子どもを育て、家族の介護をしながら働き続けることができる環境が整備され、拡充されていくことに異論がある人は少ないだろう。
だが、そもそもなぜ時短勤務の制度は育児と介護の他には適用されないのだろうか。少子高齢化対策として育児・介護休業法が整備された歴史的背景を踏まえるとあたりまえと言えばあたりまえである。一方で、ワーク・ライフ・バランスや多様性が叫ばれて久しい世の中にあって育児と介護に支援が偏っているのは、誤解を恐れずに言えば、法律がプライベートの事情に重みづけをしているとも言えまいか。
現状の時短勤務も様々な課題を抱えている。よく言われるのは、育児や介護をしていると突発的に休まざるを得ず、時短勤務をしていない社員に仕事の負担が偏るというものだ。
逆に、時短勤務をしている社員にとっては、限られた時間の中で成果を出すために人一倍集中して仕事に取り組む必要があり、それは決して楽ではない。また、周囲からの目線が気になったり、葛藤を抱えながらも相談がしづらかったり、「時短勤務だから」とやりがいのある仕事を任せてもらえず評価もされづらいなどの問題も発生しがちである。
リブセンス従業員の声
リブセンスで、時短勤務をしていたり、育児や介護をしながら働いている当事者に話を聞いてみた。
「親が手術のために入院をした頃から認知症も少しずつ進んできていて、精神的なフォローをすることが辛かった。介護をするようになった前後で仕事量は減ってしまい、現在はリモートワークを活用して親の近くで介護しながら働けているので不安は減っているが、いまだに周囲に迷惑をかけているような罪悪感を感じながら働いている部分はある。本当はもっと仕事したいけど、自分がパンクしてしまうのが分かっていて、そこのジレンマはあります」(介護をしながら働く社員)
「いつ子どもが風邪を引いて休みになるか分からないから、仕事で自分から手を挙げづらくなった。私だけかもしれないが、育児で使う頭と仕事で使う頭は違って、切り替えがうまくきかず、以前はできた仕事ができなくなり『自分、仕事できないな』という気持ちでいっぱいになった。今は周囲にうまく気持ちを吐き出すことができるようになってきたが、自分から言える人が少ないと思う。『復帰させていただいた。時短で働かせていただいている』という気持ちがある」(育児をしながら時短で働く社員)
かたや、当事者と一緒に働く上司にも話を聞いてみた。
「正直、最初はどうマネジメントすれば良いのかわかりませんでした。他のメンバーと比較するとそもそもの勤務時間は短いうえに、どうしても突発的な休みが出てしまう。仕事に対して前向きに取り組んでいて、スキルも高いメンバーではあるのですが、できるかぎり負担の少ない仕事をお願いする方が本人にとってもプレッシャーにならずに良いのかな、と思っていた時期もありました。ただ、一緒に働くうちに『時短勤務だから、休みが発生してしまうからこう仕事をお願いする』と勝手に決めつけるのは、相手にとって失礼だしお互い損だなと思うようになりました。今はフルタイムの他のメンバーと同様に、その人がやりがいを持って取り組める仕事を一緒になって考えるところから業務の設計を行っています。もちろん、時間的な制約があることは変わりませんが、そういったことも含めてお互いの考えを率直に伝え合ったうえで、よりよい在り方を模索していければと考えています」(時短勤務をしている社員の上司)
「ご家族の介護が一番大変だった時期は、そのメンバーには予算を追わない仕事を任せてきました。ただ、実家に帰って70歳になる親を見た時に『自分の親もあと10年しないうちに介護が必要になるかも』と感じて、ものごとを表面的にしか捉えていなかったことに気付きました。病欠と同じで誰にでも順番に回ってくるイベントなので、介護に関する制度はとても平等な制度なのだと捉えるようになった。『なんであの人だけよく休むんですか』という声も最初はあったが、事情を丁寧に説明していますし、他のメンバーに対してもそれぞれの事情に応じて臨機応変に対応しているので、ハレーションはなくなってきています」(介護をしながら働く社員の上司)
制度が生み出す分断
働き方の問題は実に根が深い。本質的には自分とは違う状況に置かれた他者を理解することの難しさが根底にあり「子どもがいる・いない」、「介護する家族がいる・いない」など、簡単に人を二元論に陥らせ対立構造を生み出してしまう。誰かを助けるための制度がかえって分断を生み、助長してしまうリスクも否定できない。
仕事とプライベートを両立する制度と風土を整えることは、各国、各企業が取り組まなけれならない課題である。日本では、育児・介護に対する支援策の他、時短正社員制度の普及を国が積極的に進めている。週休3日制の導入や1日の所定労働時間を6時間とする企業も出てきている。いずれも認知度や普及率はまだまだ低いと言えるが、育児や介護に限らず、だれもが柔軟な働き方ができる仕組みを整えていくことは、今後も国や企業が積極的に進めていくべきだろう。
同時に、一人ひとりの意識にも変化が必要だろう。誰もが同じ状況になる可能性がある。今だけを切り取れば不平等に見えたとしても、「明日は我が身」と考えると違った見え方がしないだろうか。分断を乗り越える道のりは長いが、小さな一歩を重ねていくしかなく、ちょっとした想像力がその一歩になることもまた間違いない。